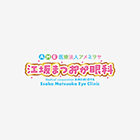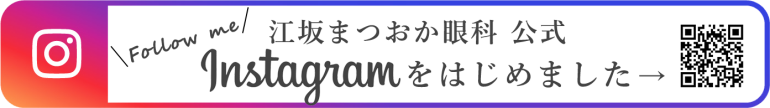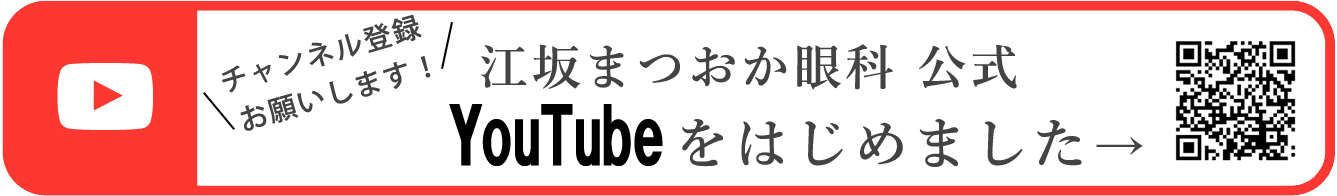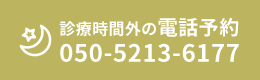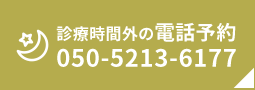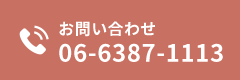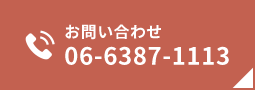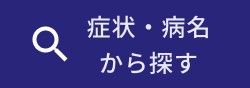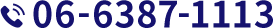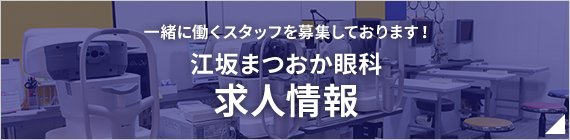フレイル(Frailty)とは、加齢によって心身の能力が著しく衰えた状態を指します。
そして、アイフレイル(Eye Frailty)はフレイルの中でも目の衰えを特に指す言葉で、加齢に伴って目の機能が低下し、視力や視覚機能に影響を及ぼす状態を指します。
アイフレイルは高齢者の生活の質(QOL)に大きな影響を与えるため、早期発見・予防が重要視されています。
京都大学の辻川明孝先生が主導する研究・啓発活動によってこの重要性に近年注目が集まっています。
ACのCMをご覧になった方も多いかと思います。
当記事ではアイフレイルの概要、発生の経緯、全身フレイルとの関係について説明します。
目次
1.アイフレイルとは?
アイフレイルは「目のフレイル」ともいえ、加齢に伴って視機能が低下する過程で現れる以下のような症状や状態を指します。
早期発見・早期対策を行うことで、視力の維持やQOLの改善が可能です。
2.アイフレイル研究の経緯:辻川明孝先生と京都大学
京都大学の辻川明孝先生は、加齢に伴う眼疾患の予防や視覚機能の維持に関する研究をリードしています。
高齢化が進む日本において、視覚機能の低下は認知症や転倒リスクの増加と関連しており、「アイフレイル」という概念を提唱することで、社会的な予防意識の向上を目指しています。
研究の主なポイント:
- 視力低下が全身のフレイル(身体的・認知的機能の低下)と関連することを実証
- 眼科的な介入により、転倒リスクや認知機能低下の進行を遅らせる可能性を提示
- 地域住民への啓発活動を通じて、目の健康診断の重要性を周知
3.全身のフレイルとの関連
アイフレイルと全身のフレイルには密接な関係があります。
全身フレイルは、身体的・認知的・社会的機能が低下する状態を指しますが、視覚機能の低下がこれらに影響することが知られています。
| 視覚機能の低下 | 全身フレイルへの影響 |
| 視力低下 | 移動・歩行困難 → 筋力低下・転倒リスク増加 |
| 視覚情報の減少 | 認知機能の低下(認知症リスク増加) |
| 社会活動の制限 | 孤独感・うつの増加(社会的フレイル促進) |
アイフレイルが全身のフレイルにつながるメカニズムの例
- 視覚情報は認知機能に大きく寄与しており、視力低下が脳の認知負荷を増加させる
- 歩行時に視覚情報が少なくなると、バランスを崩しやすく転倒リスクが増加
4.予防と対策
アイフレイルの予防には、定期的な眼科受診と生活習慣の改善が重要です。
予防のポイント
- 定期的な眼科検診:40歳以降は年1回の検査推奨
- 紫外線対策:サングラスや帽子で目を守る
- 食生活の改善:抗酸化作用のあるビタミンA・C・E、ルテイン、亜鉛などの摂取
- 全身的な健康管理:糖尿病や高血圧のコントロールが眼疾患予防に寄与
5.社会的な取り組みと今後の展望
辻川先生を中心に、アイフレイルの認知拡大を目的とした啓発活動が進められています。地域の健康イベントや高齢者向けの講習会を通じて、視覚機能の健康維持が「健康寿命の延伸」につながることを強調されています。今後、さらにアイフレイルの早期発見・予防に役立つ技術や診断ツールの開発が期待されています。
アイフレイルは目だけの問題ではなく、全身の健康や生活の質に直結する重要な課題です。
視覚機能を守るために、定期的な検査と日常的なケアを心がけることが、健康長寿への第一歩となります。