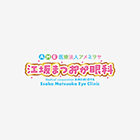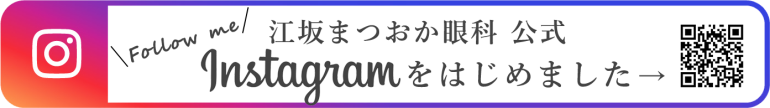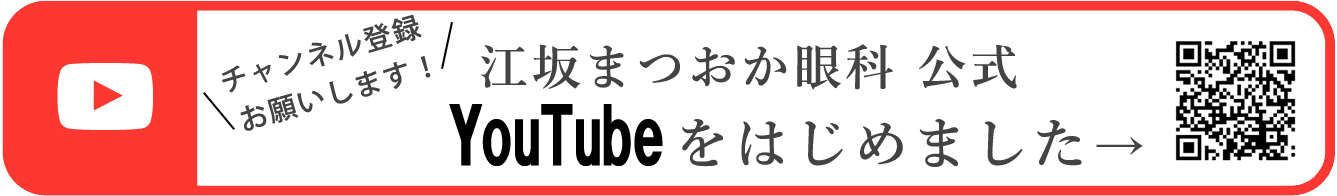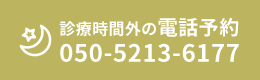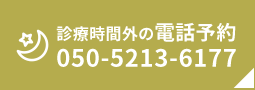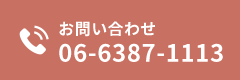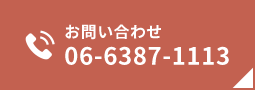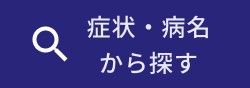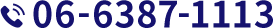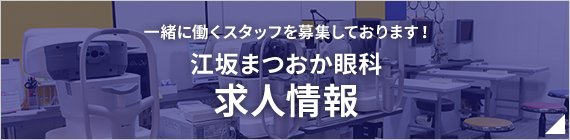ピロカルピンについて、以下のポイントでわかりやすく解説します。
1. ピロカルピンの歴史と特徴
ピロカルピンは緑内障治療薬として最も古くから使われてきた薬のひとつです。
副交感神経を刺激し、瞳孔を縮め、房水排出を促進して眼圧を下げる作用があります。
2. 最近あまり使われない理由
|
理由 |
内容 |
|
副作用が多い |
縮瞳による夜間視力低下、頭痛、眼痛、目の充血、まばたき増加などが強い。 |
|
使用感が悪い |
点眼後の異物感やかゆみがあり、患者の負担が大きい。 |
|
効果が限定的である場合が多い |
開放隅角緑内障などではより効果的で副作用の少ない新しい薬剤(プロスタグランジン製剤、β遮断薬など)が主流。 |
|
長期使用の問題 |
毛様体筋の硬化や持続的な縮瞳による不快感。 |
3. ピロカルピンの適応
- 主に閉塞隅角緑内障の急性発作の初期治療で使われることが多い。
- 開放隅角緑内障では、他の薬剤に比べて使用頻度は低い。
- 眼圧が急に上がった場合に隅角を開くために役立つ。
4. 老眼治療薬としての可能性
ピロカルピンは毛様体筋を収縮させて調節力を高めるため、老眼(調節力低下)改善の可能性があるとされています。
実際に近年、低濃度ピロカルピン点眼薬が老眼治療用として研究・実用化が進んでいる。
副作用が軽減された配合薬や低濃度処方が開発されており、近距離視力改善に期待される。
5. まとめ
|
項目 |
内容 |
|
昔からの利用 |
緑内障治療の基本薬であったが、副作用が強い |
|
使用減少理由 |
新薬の登場、使用感の悪さ、長期使用の問題 |
|
適応 |
急性閉塞隅角緑内障の初期治療など限定的 |
|
老眼治療 |
低濃度ピロカルピン点眼薬で調節力改善の期待あり |
ピロカルピンについては、下記動画「【人類みな老眼】老眼チェックの方法から目薬まで!老眼との付き合い方」でもわかりやすく解説しています。