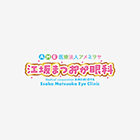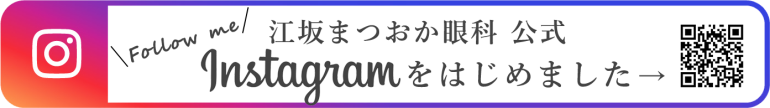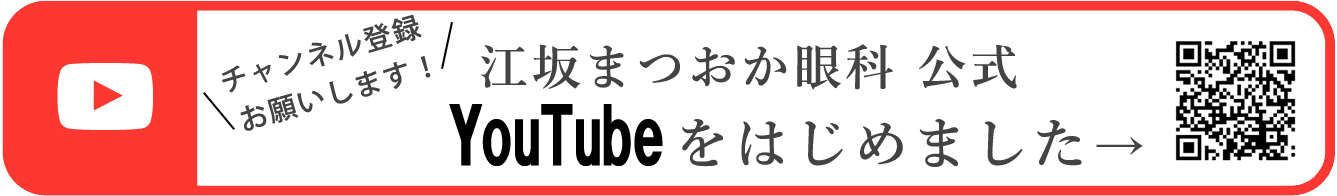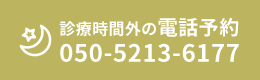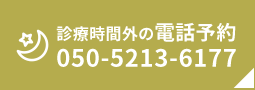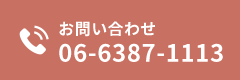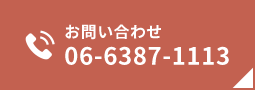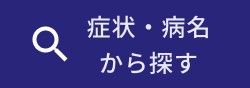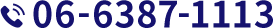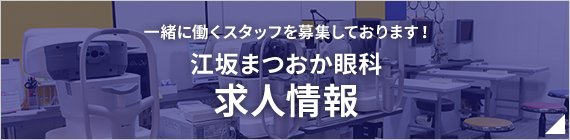目次
① 効果が続かなくなった(睡眠時間の減少・生活リズムの変化)
オルソケラトロジーは「寝ている間に角膜の形を変えて視力を矯正」します。
つまり、十分な睡眠時間と毎日の装用の継続が何より大切です。
しかし、中学生・高校生になると次のような変化が起こります。
- 部活動や塾で帰宅が遅くなる
- スマホやタブレットの使用時間が増える
- 夜更かし・朝型のリズムが乱れる
結果として、レンズを入れている時間が短くなり、形が安定しにくくなるのです。
例)
「以前は8時間寝ていたけど、今は5〜6時間しか寝ない」
→ 朝の視力が出ても、午後になるとぼやける・黒板が見づらい
「部活の遠征で装用できない日が続いた」
→ 数日で元の近視に戻る
このように、思春期の生活習慣の変化が、治療の継続を難しくすることがあります。
② 見え方の安定が悪くなった(角膜形状の変化・成長期の影響)
オルソケラトロジーは角膜(黒目の表面)の形を微妙に変えることで焦点を合わせます。
成長期には、角膜や眼軸(眼の長さ)も変化するため、「以前と同じレンズでは合わなくなった」「視力の戻りが早くなった」などが起こります。
例)
「1年使っていたけど、急に朝ぼやける」
→ 成長で角膜カーブが変わり、レンズがずれやすくなった
このような場合、レンズの再設計や再作製が必要になりますが、
そのたびに費用がかかるため、やめる決断をするご家庭もあります。
③目のトラブルや違和感(ドライアイ・花粉症・コンタクト負担)
成長とともに、目の環境も変化します。
- 長時間スマホやパソコンを使う
- 受験期のストレスで瞬きが減る
- 花粉症が始まる
これらはドライアイやアレルギー性結膜炎を引き起こし、夜の装用時に「ゴロゴロする」「痛くて眠れない」と訴えることが増えます。
例)
「春になると装用できない」「寝ている間に外れてしまう」
→ 角膜の乾燥やアレルギーでフィッティングが不安定
このような場合は、点眼や一時中止で改善を試みるものの、
症状が続けば「裸眼や眼鏡に戻る」という選択になります。
④ ケア・衛生管理の負担(特に中高生・寮生活・部活遠征)
オルソケラトロジーは、毎日の洗浄・すすぎ・保存液の交換など、ハードレンズ並みのケアが必要です。
また、清潔な環境での装用が前提です。
例)
「部活の合宿先で洗浄液を忘れた」
「寮で水道が共用なのでケアが不安」
「疲れてそのまま寝てしまった」
こうした“ちょっとした油断”が、角膜感染症のリスクにつながります。
医師が安全を最優先に「いったん中止しましょう」と判断することもあります。
⑤ コスト・費用の問題(自由診療)
オルソケラトロジーは保険適用外の治療で、初期費用は10〜20万円前後、レンズ交換・定期検査も必要です。
例)
「高校生になってから、コンタクトを使う日が減ったのに費用がもったいない」
「大学進学で一人暮らしになるから、管理が心配」
こうした現実的な事情から、高校卒業を機に中止するケースも多く見られます。
⑥ 近視抑制の限界と期待のギャップ
最近は「近視の進行を防ぎたい」という目的で始める方が増えました。
しかし、進行は遺伝や生活環境(屋外活動・スマホ時間)にも左右されます。
例)
「オルソしても、近視が少しずつ進んだ」
→ “止まる”わけではなく、“ゆるやかにする”治療だと理解されにくい
近視抑制効果を正しく説明しても、
「思ったほど効果がなかった」と感じてやめる方もいます。
⑦ やめた後のフォローアップが大切
オルソケラトロジーをやめても、
- 近視抑制点眼(低濃度アトロピン)
- 遠近両用ソフトコンタクト
- 屋外活動・照明環境の改善
など、代替手段や生活改善で視力を守ることは可能です。
治療をやめる=失敗ではなく、「今の生活に合った方法を見直すタイミング」と考えることが大切です。
まとめ
|
主な理由 |
背景・きっかけ |
よくある年齢層 |
|
睡眠時間の減少 |
部活・塾で帰宅が遅い |
中高生 |
|
見え方の不安定 |
成長による角膜形状変化 |
中学生〜高校生 |
|
装用時の違和感 |
ドライアイ・花粉症 |
小6〜高校生 |
|
ケアの煩雑さ |
忙しくて手入れ不足 |
中高生・寮生 |
|
費用面の負担 |
継続コスト |
高校〜大学生 |
|
効果への不満 |
期待と現実のギャップ |
保護者・学生とも |
オルソケラトロジーを続けられなくなる理由や失敗談については、 下記動画「近視治療のオルソケラトロジー、失敗することもある!? 眼科医がみた失敗談!」でも解説しています。