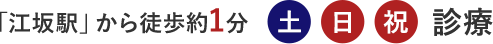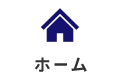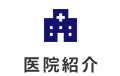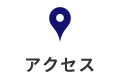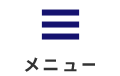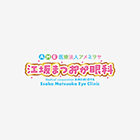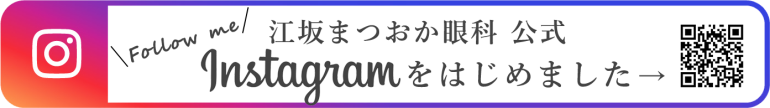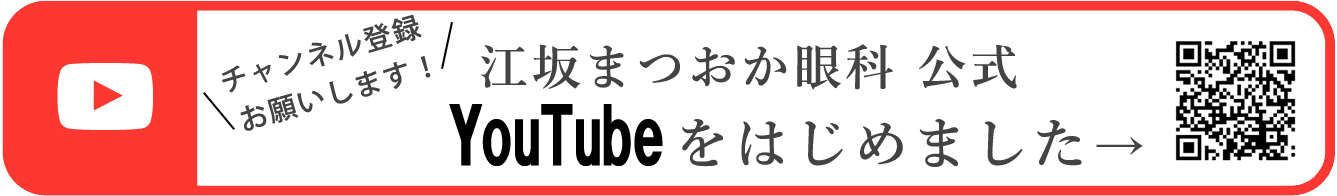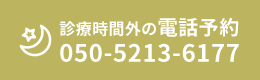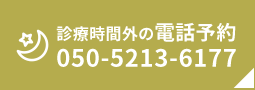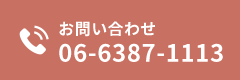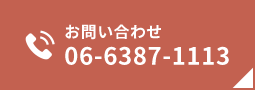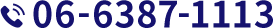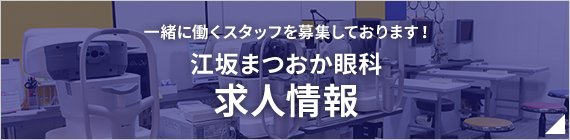【3,000万人の現代病】花粉症 発症のメカニズムや有効な対策方法について

花粉症という病気は知らない人はほとんどいないと思います。
非常に有名な病気の一つですが、その歴史を紐解いていきましょう。
患者さまからよくご質問いただく内容について動画でも解説しております💡ぜひごらんください!
目次
花粉症という言葉はいつからでてきたの?
はじめに、花粉症という言葉がいつから出てきたのか?からみていきましょう。
実はこの花粉症という病名は、近年になって誕生した病名です。日本で、最初に花粉症として診断された症例は、1961年の患者さんです。日本で初めて花粉症として診断された患者さんの原因物質は実はブタクサという植物の花粉でした。
このブタクサは、戦後にアメリカの進駐軍が日本へ落ち込んだものでした。ブタクサは、キク科の一年草で、外来種です。 繁殖力が強く、戦後に全国へ花粉が飛散され、初めて花粉症という言葉が世間で認知されるようになりました。
その後、スギ花粉による花粉症が有名になりました。スギ花粉症というのは戦後に植林が進んで出てきた病気であり、日本特有のものとなっています。
世界の花粉事情について
次に世界の花粉症事情ということについて見ていきたいと思います。世界の三大花粉症と言われるものがあります。ヨーロッパを中心に見られるイネ科のカモガヤ花粉症、アメリカが中心のブタクサ花粉症、日本のスギ花粉症。これら3種類以外にも花粉症の原因となる植物は世界各地で確認されております。
それらの総数は、現在の数ではだいたい60種類くらいと言われていますが、今後研究が進めばさらに増えるだろうと予測されます。原因になる物質が同定されれば、種類が増えるという事情があります。
日本のスギ花粉が急に増えた理由は?
どうして日本のスギ花粉症に関して、戦後に増えてきたのでしょうか?
スギ花粉症は、1964年に初めて報告をされています。戦後にスギが急激に増えた事情ですが、1960年の所得倍増計画、その後の高度成長期、政府の人工林を拡大造林するという政策が進められました。
その結果、現在では、日本の森林の約4割が人工林、人工林の4割がスギとなっています。スギの木の数がすごく増えたので、スギ花粉症が増えたということは確かです。
食生活も関係ある?

一方で、人の体質の変化も原因ではないかと言われています。
戦後に、食の欧米化が進み、肉食が非常に増えたということがあります。食生活の変化は、体質の変化をもたらし、場合によっては、アレルギー体質になりやすい体質になる可能性があると言われています。
脂肪酸というものがありますが、魚の脂肪酸というのは不飽和脂肪酸であり、動物性脂肪というのは飽和脂肪酸が主体と言われています。
飽和脂肪酸の過剰摂取により、アレルギーを起こしやすい体質になる可能性が示唆されています。
日本人の3,000万人が花粉症
花粉症の有病率ですが、1998年 19.6%、2008年29.8%、2019年42.5%ということです。10年に10%増加し、今後も増加し続けると予測され、国民病と言われています。
生命を脅かすような病気ではありませんが、生産性が非常に落ちますので、国を上げて対策をしないといけない状況になっています。
花粉症のメカニズム
花粉症という病気が、どのようにして起こるのか?そのメカニズムについて見ていきたいと思います。
花粉が体の中に入って病気が起こるわけですが、花粉がまず最初に体内に侵入した場合、身体はこの花粉を異物として認識します。いわゆる免疫反応というものですが、花粉を効率的に排除するような体制を整えようとするのです。
花粉だけを特異的に認識する抗体を作製します。抗体には種類がありますが、花粉に対するものは、IgE抗体というものが主体です。そして、このIgE抗体は、花粉が次に侵入した時には、花粉を一気に排除しようとして、過剰に反応するのです。
本来、免疫反応は体にとって良い反応ですが、花粉症の場合は、その免疫反応が過剰になり過ぎて、生活に支障が出てしまう状態と言えるでしょう。
このように、免疫反応が過剰に働き過ぎて、体にとってマイナスに働いてしまう場合をアレルギーと言います。従って、花粉症という病気は、アレルギーの一種ということになります。
通常アレルギーという病気はいろんな異物に対して起こるわけですが、これを抗原またはアレルゲンと言います。こういったアレルゲンに対する反応のことを、アレルギーと言います。そして、花粉に対するアレルギーのことを花粉症というわけです。
発症のメカニズム
発症メカニズムについてもう少し詳しく見ていきましょう。まず体に花粉が入ると、それを異物として認識するために、体内に侵入した異物を何でも食べる細胞、マクロファージが、この花粉を食べます。
マクロファージは、花粉を消化してバラバラにして、抗原という細かい抗原ペプチドに分解します。マクロファージは、分解された抗原ペプチドを、細胞表面に提示し、リンパ球という細胞に情報を伝達します。そして、情報を受け取ったリンパ球は、抗体を産生するシステムへと情報を拡散していきます。
抗原特異的なIgE抗体が、大量に産生されます。そして、花粉の次の侵入に備えるのです。抗体は血液中に存在し、体内で異物を認識して抗原を捕まえるようなものです。
IgEは、血液や粘膜内にある肥満細胞にくっついて、異物が入って来たときの準備を整えるわけです。Redy-To-Goな状態です。そこに、アレルゲンが入ってくると、IgEに抗原が捕捉され、抗原抗体反応がおこり、肥満細胞が活性化されます。ヒスタミン等のケミカルメディエーターが分泌され、アレルギー炎症をおこすことになります。
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目の充血や痒みなどの症状が起きます。肥満細胞が放出するものをアレルギー誘引物質は、ケミカルメディエーターと言いますけれど、様々なものがあります。
一番有名なのがヒスタミンという物質その他にプロスタグランジンやロイコトリエンいう物質も出ます。これらの物質がスイッチとして働き、血管拡張や血管透過性亢進、かゆみ、気管支収縮などの反応を引き起こします。
20分でわかる!花粉症・アレルギー検査
当院ではアレルギー検査を実施しております。詳細は下記ページをご覧ください。
花粉症の対策について
「花粉症はどうやって治療していけばいいのか?」について解説していきます。「花粉症は治らないの?」という質問をよく患者さんから受けます。単刀直入に言いますと、基本的には、治らない病気であるという認識です。
なぜ治らないかというと、体質ということだからです。アレルギーの体質と理解してください。生まれた持ったものなので、致し方ないというところはあります。
最近では、減感作療法という体質を改善していく治療法ができてきましたが、体質改善には相当の時間を要するようです。このように、体質というのはなかなか改善しにくいものです。
もちろん、世の中には「花粉症ってどんな感じでしんどいの?」というような、羨ましい体質の方もいらっしゃいますので、これはもう基本的には持って生まれたものだと考えて頂くしかないと思います。
実際に、アレルギー体質の方というのは、花粉のみならず、ハウスダストや食べ物など、いろいろなアレルギーも持っている方もいらっしゃいます。実際私もアレルギー体質ですので、毎年、花粉症に悩まされていますが、旅行などで埃っぽい部屋に行ったりすると、すぐにくしゃみが出て、そのあとひどいことになったりします。
体質なので仕方ないですが辛いですね。だからこそ、なるべく症状が発症しないように、また、症状が出たとしてもなるべく軽症で済むように、備えることが大切になってきます。そのためにも、花粉症という病気に関して、理解を深めていただくと幸いです。
花粉症の病態は、花粉に対するアレルギー反応ですので、アレルギー性鼻炎、あるいは、アレルギー性結膜炎などが主体となる病気です。アレルギー性鼻炎は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状が、アレルギー性結膜炎は、充血、眼脂、掻痒感が主体です。いかにして、これらの症状に対策するのかということが大切になります。
一番有効な対策は、とにもかくにも抗原の暴露を避けることです。アレルゲンに接触しないということが一番大切です。「具体的にどうすれば、花粉に触れる機会を少なくしていけるか?」ということを挙げていきます。花粉症の時期になると、テレビで花粉の飛散予測というのが、天気予報と一緒に紹介されます。
花粉が飛散する時期は、是非ともニュースからそういった情報を集めて、外出時間や場所の参考にされてはいかがでしょうか?地域によって、花粉の多い場所、少ない場所など特徴がありますので、大変参考になります。
また、日中より夜間の方が花粉の飛散が少なかったりします。なるべく、花粉の多い地域や時間帯のお出かけを控え、可能であれば、花粉の少ない場所や時間帯に外出時間を変えてやることは、症状の改善に有効な方法かと思います。
2年ぶりの花粉症?
例えば、毎年花粉の飛ぶ時期っていうのは1月ぐらいから、2月、3月、4月と続くわけで、毎年、同じ時期に同じような症状が出るわけです。先日、いらっしゃった患者さんのお話ですが、「今年もやっぱり1月になって花粉症が出したので、お薬をください!」とおっしゃるわけです。
ふとカルテをみると、2年ぶりのご来院でした。「去年は大丈夫だったんですね!」とお話ししたら、「そうなんですよ!シンガポールにいたんです。シンガポールに行ったら花粉症全くでなくて快適でした!」とのこと。暖かいシンガポールには、針葉樹が生えてないみたいです。
すなわち、スギの木が生えていないということで、杉の花粉ない、アレルゲンがない環境だったと考えられます。アレルゲンがない環境では、花粉症は発症しないということがよくわかりました。アレルギーにとって、いかに抗原に暴露されないということが重要かということです。
しかしながら、この患者さまは、今年は日本に帰ってきたので、花粉症を発症してしまったということです。従って、花粉症の体質は変わってなかったということです。というわけで、早速2年前と同じお薬を処方させて頂きました。
とにかく花粉を避けるのが吉!

どうしても都合がつかず、花粉の多い場所や時間帯に外出しないといけない場合は、できるだけ花粉に触れる機会を少なくする努力をしましょう。
保護用のメガネや、ゴーグルをつけて外出するのも有効です。また、外出後は、家に花粉を持ち込む可能性がありますので、要注意です。花粉の多い場所へ出かけた後は、花粉がたくさんついている衣服で帰ってきます。
そのまま部屋に入ると、部屋に花粉を持ち込んでしまい、部屋の中でも抗原に暴露され続けるということで、苦しい思いをすることになりかねません。対策としては、玄関に入る前に、一旦、服を叩いて、花粉を服から少しでも落とし、もち込む花粉を少なくすることが有効です。
部屋に入った後は、すぐに、手洗い、うがいをしてやることが有効です。また、鼻うがいも、アレルゲンを排除するという意味では有効です。なかなか聞きられない方もいらっしゃると思いますが、鼻の粘膜についた花粉を、生理食塩水を人肌程度に温めて鼻の中に流し込み洗浄する方法です。
室内のアレルゲンを少なくする方法としては空気清浄機で花粉を吸引する方法や、加湿器をつけて少しでも飛んでいる花粉を落としてやるのも有効です。
窓を開けて換気する場合は、時間帯に気を付けて頂けると良いと思います。早朝や夜間など、花粉の飛散が少ない時間帯を選んでいただくことで、花粉の部屋への持ち込みを少しでも少なくなるできます。
外出時の服装ですが、セーター等の毛足が長く、花粉をキャッチしやすいものは避けていただき、ナイロン素材などツルツルしたものを着ていただくことで、部屋に持ち込む花粉を少なくすることができます。
アレルギーは、疲れた時に発症しやすいです。そういった意味では、なるべく疲れないように、規則正しい生活を送って、疲労やストレスをためない生活を心がけるというのも、アレルギー対策としては有効です。